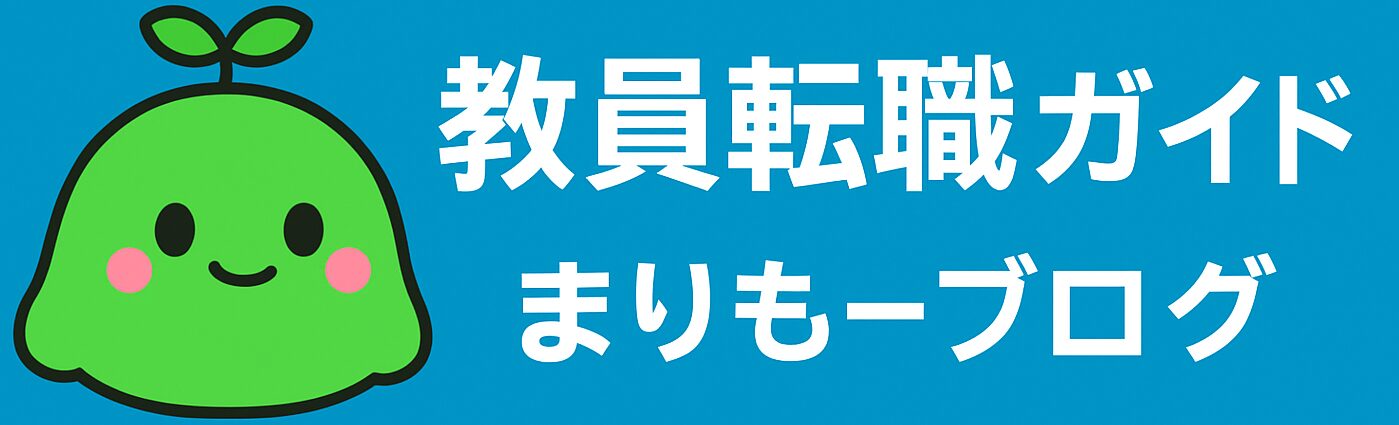元教員の体験談「転職前に知っておきたい外の世界」

教員として働いていると、どうしても外の世界と関わる機会が少なく、視野が狭くなりがちです。
そのため、いざ転職を考えたときに「他の仕事との違い」に戸惑い、ギャップに苦しむ可能性があります。
実際、私自身も教員を辞めてから外の常識との違いに驚き、最初はかなり戸惑いました。
だからこそ、転職活動を始める前に「教員以外の世界を知っておくこと」がとても大切だと感じました。
この記事では、私の体験をもとにどんな違いがあるのかをお伝えします。

最後までお付き合いください!
教員の働き方と一般企業の違いとは?
1.勤務時間への意識
一般企業では、残業代が支払われることもあり「勤務時間への意識」がとても強いです。
私にとってはこれがとても新鮮で、「これが社会の普通なのか」と驚きました。
勤務時間中は業務に集中し、時間が過ぎればきっちり帰る。
これが当たり前の感覚です。

当然「仕事が終われば」だけどね。
一方で教員時代は、勤務時間中でも職員室でおしゃべりや休憩が見られ、逆に勤務時間を過ぎてもだらだらと仕事を続けることが多くありました。そもそも定時が17時でも、部活動が終わるのが19時なので、時間内に帰れることはほとんどありません。

毎日2時間の残業確定か…(しかも手当なし)
もし今の職場で、勤務時間中に集中せずにおしゃべりばかりして、挙げ句の果てに残業代を請求したら…間違いなく大問題になります。
「勤務時間中に集中して成果を出す」という意識は、転職して改めて痛感しました。
2.感情vs利益
公立の学校にとっては「利益を追求する」という概念がありません。
そのため、何かを判断するときの軸の1つに「生徒のために」という、「感情ベース」が元となります。
例えば、新しい企画(プロジェクト)を提案するときの基準は次のようなものでした。
- 生徒にどんなメリットがあるか
- 教職員の負担はどの程度か
- 予算的に実施できるか
一方で、現在の会社では考え方がまったく異なります。
- 利益はいくら見込めるか
- 自社ブランドへの影響はどうか
- 想定されるリスクと対策
ここには「感情ベース」の視点はほとんど出てきません。
企業は利益を出さなければ存続できないため、常に採算性が求められます。
正直、この「利益を前提とした考え方」に慣れるまで、私はかなり時間がかかりました。
しかし逆に言えば、こうした視点を持つことができたことで、社会全体の仕組みを理解できるようになったと感じています。
3.自腹購入の必要性
教員時代は、思い返すとかなりの額を自腹で使っていました。
「予算がないから仕方ない」と思っていましたが、正直負担は大きいものでした。

なんだかんだ、年間3万円以上使ってたかなあ
特に、一年に一度しか使わないクラスTシャツは高額なうえ実用性も薄く、「できれば勘弁してほしい」と思っていました。ただ、生徒の手前「買わない」とは言えず、結局自腹を切るしかありませんでした。
実際に自腹で購入していたものの例
- PC周辺機器(無線マウス、無線キーボード、モニター)
- 学校行事用のクラスTシャツ
- 行事後に配る生徒へのお菓子
- 授業で使用する備品
- 部活動の備品
一方で転職してから驚いたのは、必要な備品は申請すれば会社の経費で購入できることです。
PC周辺機器はもちろん、場合によっては交際費まで申請できます。
初めて経費精算をしたときは戸惑いましたが、「これが普通なのか」と大きなカルチャーショックを受けました。
転職して気づいた、教員の強み
転職活動を始めた当初、正直「自分の強み」が全く分かりませんでした。
教員の仕事は授業や部活動指導などが中心で、成果を数値化するのが難しいからです。
さらに、相手の多くは生徒であり、大人を相手にする機会は限られています。
これも「他業界で通用する強み」とできない原因の一つでした。
教員として働いているときは、その環境が当たり前すぎて「教員ならではの強み」に気づけませんでした。しかし、転職して外の世界に出てみて、初めてその価値を実感しました。
ここでは、私が転職後にあらためて認識した教員の強みを3つに絞って紹介していきます。
1.人前で話す能力
教員時代は毎日、大勢の生徒を相手に授業をしていました。
ただ話すだけでは生徒はすぐに飽きてしまうので、抑揚をつけたり、対話型・参加型を意識したりと工夫が必要でした。
その経験のおかげで、現在の会社でプレゼンをする際にも「分かりやすい」「聞きやすい」と褒めてもらえることがあります。これは間違いなく教員として培った強みだと感じています。
もちろん今でも人前で話すと緊張はしますが、「苦手」ではなく「むしろやりがいを感じられる」という感覚です。
2.マルチタスク能力
教員時代は同時並行でさまざまな業務をこなしていました。
- 教科指導
- 担任業務
- 部活動指導
- 行事の企画運営など複数の係の仕事
授業の空き時間に業務を進めようとしても、生徒指導や突発的なトラブルが飛び込んできて、大混乱になることも珍しくありませんでした。

空きコマが少ない曜日に限ってトラブル起きがち。
そのため、限られた時間の中で効率よく計画を立てて仕事を進める力が自然と鍛えられました。
この経験は、転職後の仕事にも大きく生きています。
今の会社では案件数は多いものの、業務の種類は教員ほど複雑ではありません。
やはり「教員のマルチタスク力はすさまじい」と改めて感じています。
3.人間味のある温かさ
教員の仕事は言うまでもありませんが、単に知識を教えるだけではなく、生徒一人ひとりの人格を形成する目的があります。
教員として働いていると、同僚の先生たちがいかに人間的で優しいかということを強く実感しました。温かみのある人の割合が圧倒的に多く、生徒だけでなく教員同士の関係にもその温かさが浸透しています。
こうした環境を経験することで、「教師は聖職である」という言葉の意味を、身をもって理解することができました。
転職後も、お客様から「話しやすい」「相談しやすい」と言っていただけることが多くありました。これは教員時代に、生徒や保護者と真剣に向き合ってきた経験、そして同僚から受けた温かさが基盤になっていると感じています。
ビジネスの場では数字や効率が重視されがちですが、最終的に成果を生むのは「人と人との信頼関係」です。教員経験から身についた、人間味のある温かさは、どんな仕事にも通用する普遍的な強みと言えるのではないでしょうか。
元教員のリアルな話に救われた
転職前の私は、正直自信がありませんでした。
そもそも転職できるのか、教員以外の仕事でやっていけるのか、不安ばかりが頭をよぎっていました。
そこで、元教員で現在民間企業で働いている方に実際に話を聞くことにしました。
そのおかげで、漠然とした迷いや不安が少しずつ整理され、行動するきっかけを得ることができました。
転職という選択は怖いものです。
そして、実際に経験した人にしかわからないリアルな感覚があります。
転職を考えている方は、一度元教員の方の話を聞くことを強くおすすめします。